生薬
カンレンソウ(旱蓮草)

「夏至」ごろから秋にかけて収穫される「旱蓮草(かんれんそう)」は、別名「鱧腸(れいちょう)」「金陵草」とも言われます。
基原はキク科の「タカサブロウ」の全草。サポニン・タンニン・ビタミンAが豊富で、徳川 3 代将軍家光公もこのタカサブロウのおひたしがたいそう好物だったようです。収斂性があり強壮作用に優れ、肝腎陰虚や陰虚内熱など過熱傾向にある体質や不正出血などの緩和に用いられます。更年期にありがちなツライ不定愁訴の緩和にも役立ちます。
関連商品
-

ばんらんこん(板藍根)
アブラナ科のホソバタイセイの根を乾燥したもの。インフルエンザ等ウイルス性疾患に効果が認められている。 板藍茶やのど飴とした製品がある。
-

コウブシ(香附子)
カヤツリグサ科のハマスゲの球茎を乾燥させたもの。月経不順、月経痛、神経痛などに適用されます。
-
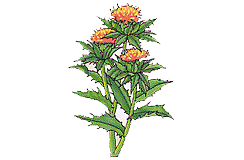
コウカ(紅花)
キク科のベニバナの花を乾燥させたもの。初夏にオレンジの花を咲かせます。生薬としては紅花(コウカ)と呼び、温性で、瘀血(おけつ:血液循環の不良)を改善する効能があります。
-

五行草茶(ごぎょうそうちゃ)
スベリヒユは、日本では、ウマヒユやヒョウの名でも呼ばれています。茎が赤、葉が緑、花が黄、根が白、種子が黒いことから中国では五行草とも呼ばれ、健康維持のために大切な食材として人々に親しまれてきました。このスベリヒユを手軽に摂れるようにしたのが「五行草茶」です。
-

トウキ(当帰)
女性の健康な体づくりに欠かせない生薬として知られるセリ科の植物。血を補い体を温め、血の巡りをよくすると言われ、中国では昔から「女性の宝」として重宝されてきました。
-

タンジン(丹参)
数ある薬草の中でも、最も優れた血液サラサラ効果を持つと言われているシソ科のタンジンの根を乾燥させたもの。











